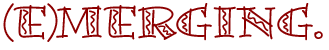
連載 『女性学』って何? 第2部
フェミニスト心理学の苦悩
フェミニスト心理学の源流
第2次フェミニズムの活発化にともない、女性学は既存の学問から分かれる形で登場しましたが、当初の女性学クラスは第1部で述べた通りコンシャスネス・レイジング(CR)を大学に持ち込んだような内容でした。 このCRが今の「フェミニストセラピー」の原形と私は考えていますが、この事から分かる通り、第2次フェミニズムは心理学にも大きな影響を与えました。 では、フェミニストセラピーやフェミニスト心理学とは既存のカウンセリングや心理学とはどのように違うのでしょうか。
その前に、当時の心理学の情勢について説明する必要があります。 今からは考えもつかない事ですが、第2次フェミニズムが登場した60〜70年代のアメリカではCarl Rogersによるヒューマニスティック心理学やAbraham Maslow、Rollo Mayといった実存主義心理学が全盛期にありました。 ヒューマニスティック心理学や実存主義心理学ではカウンセラーとクライアントの関係に対する再考が行われ、病気への治療ではなく人間的な成長のためのカウンセリングが推奨されました。 Rogersは人々が持つ「自己を肯定されたい」という願望に注目してカウンセリングに役立て、またMaslowは人間が自己実現するには様々な条件が欠かせないとしてかの有名な「欲求の階層」を作り上げました。
フェミニストセラピーはこのようなヒューマニスティック・実存主義心理学をさらに押し進め、同時にCRの政治性をも統合させて始まりました。 フェミニストセラピーの特徴としては(1)文化的多様性に対する理解と配慮、(2)クライアントとの個人としての平等な関係、(3)セラピスト自身の責任ある自己管理、(4)社会的問題への関心、の4つが挙げられます。
このうち、(1)と(2)はヒューマニスティック心理学でも行われていた物ですが、フェミニストセラピーではより先鋭になりました。 例えば、ヒューマニスティック心理学でもクライアントを一個の人間として尊重するという事は行われていましたが、フェミニストセラピーでは場合によってはセラピストとクライアントの垣根も取り払って大人の女性同士(今はともかく当初はフェミニストセラピーを実践した男性も、フェミニストセラピーを受けた男性もいなかったと思われます)として対等な立場に立とうとしました。(注1)
これは、言うまでもなく正統派のカウンセラーから見てとんでもない事であり、ヒューマニスティック心理学から見ても行き過ぎと受け取られる態度でした。 正統な心理学ではセラピストが効果的に治療を行うには権威と信頼によって威厳を保つ事が必要で、クライアントと対等になろうだなんて言語道断だったのです。 すぐにも「対等な個人として友人になってしまい、カウンセリングに悪影響が出たらどうするのだ」という批判が聞かれました。
これに対処するのが上で挙げた特徴の第3点、徹底した自己管理です。 セラピストはクライアントと個人として対等な関係を築くよう努力するが、同時にセラピーの目的に悪影響を与えないよう徹底的に自己管理する責任があるという物で、実際にフェミニストセラピーの看板を掲げている人のどれだけが厳密な意味でフェミニストセラピーを実践しているかは分かりませんが、理論的にはフェミニストセラピストは通常のカウンセリング以上に高度・専門的な訓練を受ける必要があるとされました。
第4点の「社会的問題への関心」というのは言葉で言うと軽いですが、実際にはこれがフェミニストセラピーの理念の中枢でもあります。 クライアントの女性が欝や不安症などの症状を訴えて来た時に、ヒューマニスティック心理学を実践するカウンセラーなら問題は何らかの理由で彼女が自己実現を阻まれていると考え、カウンセリングによって彼女自身の成長を助けようとするでしょう。 フェミニストセラピストはそれを十分とせず、ジェンダーによって彼女を抑圧する社会の構図こそが本来の問題の大きな部分を占めると考えます。 こうした前提に立つ以上、個々の女性が成長するだけでは問題の解決にならず、社会的な変革が求められます。
このような特徴も、もちろん既存の心理学から強烈な批判を受けます。 カウンセラーは政治的に中立でなければならず、クライアントに特定の政治思想を吹き込むなど非倫理的である、と。 一方、フェミニストセラピストは女性クライアントに社会的抑圧に気付かせるのは事実を直視させる事に他ならず、彼女達自身に精神的苦痛の責任があるように感じさせる既存の心理学の方が問題であると反論します。
ジェンダー理論・アンドロジニー理論の発展
フェミニストによる心理学エスタブリッシュメントへの批判では、Phyllis Cheslerの「Women and Madness」(1972)が代表的です。 彼女は、男性を正常として定義し、女性をまるで「不完全な男性」であるかのように記述する既存の心理学を徹底的に批判します。 古くは「女性は男根願望に苛まれており、男児を出産する事によって精神的な安定を取り戻す」と主張した精神分析が象徴的ですが、例えば多くの女性が受動的である事を女性が精神的に異常である根拠としながら、主体的で積極的な女性もまた「おかしな女性」として異常扱いを受けるというようなパターンをCheslerは発見します。 すなわち、彼女は既存の心理学が決して政治的に中立である訳ではない事を明らかにしたのです。(注2)
心理学が政治的に中立でないとすると、これまで当然の事として受け入れられていた心理学上の見解にも疑念が浮かびます。 単発の研究者としては、20世紀初頭に地道な調査によって「男性は個々の能力がまちまちであり、最も適した職を選ぶために教育が必要だが、女性はみな主婦にしか適さないのだから教育は必要ない」という心理学上の「定理」を反証したLeta Stetter Hollingworthのような優れた女性の心理学者がいたのですが、心理学に潜む男性優位主義が徹底的に批判されたのは第2次フェミニズム前期においてです。
これには2つの側面があります。 まず第一に、男性による勝手な女性理解の批判。 上で挙げたような「女性は不完全な男性」と見なす立場や、男性は生物学的に優位であるとする立場などが批判されました。 と同時に、男性と女性を全く同質であると考え、男性を調査するだけで人類全体についての調査をしたと考えるのも問題でしょう。 例えば、新薬を開発するなら、発売する前に男性だけでなく女性にも安全である事を確認するのは必要ですし、出産など女性に特有の経験を全く無視して女性の心理を理解する事はできないはずです。
「女らしさ」が問題だと考えるフェミニストは、われわれが男女の性差と呼ぶものには肉体的・生物学的な差とは別に社会的に構築されるものがあると主張しました。 これがいわゆるジェンダー理論のはじまりです。 「女性は作られる」との名言を残したSimone de Beavoirに続くリベラルフェミニズムの系譜では、社会的に作られる性=ジェンダーの作成過程に注目し、「女らしさ」とされる事が多くの場合社会化の産物であり、女性を抑圧する装置として働いている事を明らかにしました。
「女らしさ」の批判に続いて登場したのがいわゆる「アンドロジニー」の理論です。 「アンドロ(男性)」+「ジニー(女性)」を組み合わせたこの言葉は、「男らしさ」と「女らしさ」を対立する概念ではなく、両方を併せ持つ事は可能であるという考え方ですが、「Toward a Recognition of Androgyny」(1973)の著者Carolyn Heilbrunらによって理論化され、Sandra Bemらのフェミニスト心理学者が膨大な調査を積み重ねる事によって一般の心理学者にも認められるようになりました。 その後、フェミニスト理論としてのアンドロジニー論は勢力を失いますが、今も教育の分野において「男らしさ、女らしさにこだわらない教育をしよう」という形で大きな影響を与えています。
科学的心理学からの逸脱
ところが、70年代の中盤以降になるとフェミニズム理論に大きな変化が起こります。 「女らしさ」を抑圧装置として徹底的に批判するリベラルフェミニズムから、次第に「女性の経験」「女性の知恵」「女性の感性」を強調する女性中心主義フェミニズムに比重が移ったのです。 心理学においてこの転換点となったのはJean Baker Millerの「Toward a New Psychology of Women」(1973)です。
Millerは本来精神分析の専門家ですが、彼女は歴史的な抑圧を受けた事によって女性はより高度な性質を身に付けるようになったと考えます。 「女らしさ」が抑圧によって押し付けられた事は事実だが、その「女らしさ」こそ実は「男らしさ」より優れた性質であり、女性が「男らしさ」や「アンドロジニー」を身に付ける事は女性の解放でも何でもないと考えるのです。 彼女が賞賛する「女らしさ」とは、優しさや愛情など人間関係の一番大切な部分であり、それが抑圧の結果得た物だとしても失うのは惜しすぎるという訳です。 例えば、男性が理性的で女性は感情的とされていた事も、感情的である事の方が人間として本来の姿であり、「理性的」にならざるを得ない男性よりよほど優れているとMillerは主張します。
「男性と同じように働くのが女性の解放に繋がる」と考えたBetty Friedanが「The Feminine Mystique」(1963)を書いて全国に反響を巻き起こしてからMillerの登場までその間ほんの10年。 フェミニズムの外部にいる人から見てフェミニストとは何を主張する人たちかさっぱり分からなくなったのも無理がないと言えますが、70年代後半に向かってフェミニズム理論はMillerが先鞭を付けた女性賛美の方向に突入します(ただし、大衆行動としてのフェミニズムは常に男女同権を求めるリベラルフェミニズムが主流でした)。(注3)
フェミニズム心理学の分野でも、女性の「優れた」性質についての研究が始まります。 一例を挙げると、道徳観念の発達の研究で有名なCarol Gilliganがいます。 彼女はKholbergという男性の心理学者が行った研究で「女の子は男の子と比べて道徳観念が一定以上は発達しない」という結果が出た事を疑問に思い、研究の過程を検証し、その問題点を明らかにしました。
Kholbergの研究では「スミス氏の妻は重病で、高価な薬を飲ませなければ死亡してしまう。 しかしスミス氏にはお金がなく、薬屋と値段の交渉をしたが安くしてもらう事はできなかった。 スミス氏は薬屋から薬を盗むべきか?」のような問題が与えられ、その答えによって道徳観念のレベルを調べていました。 回答は「はい」か「いいえ」ではなくその理由付けで評価され、「とにかく盗むべき」「法律は犯しては駄目」のような単純な回答は道徳が低く、「犯罪は確かにいけないが、命の方が大切だからやむを得ない」「その薬の値段が高いという事は、他にも大勢買えずに困っている人がいるはずだが、盗むともっと高くなってしまうので他の人に悪い」のような回答はより高い倫理感を表わすとKholbergは考えました。
ところが、男の子は年齢に応じて期待された通りの論理的な回答をよこすのですが、女の子はかなり上の年齢でもはっきりとした回答を出さないとKholbergは報告します。 これは彼女たちが確固とした道徳観念を持たないためであると彼は結論付けるのですが、Gilliganは回答が出なかった理由をより深く追及します。
その結果分かったのは、研究に参加した女の子の多くが設問の不条理さそのものに疑問を抱いているという事でした。 まず、ここでは「スミス氏」の行動について問題になりながらスミス氏夫人の意見が全く出てきません。 さらに、ここでは答えが「盗む」「盗まない」の2つに限定されていますが、女の子の多くは「もっと他に方法があるはず」と、誰も傷つかない解決方法をいろいろと考え出そうとしたようです。 Gilliganはこの結果を受け、設問の枠内で一定の方程式に基づいて答えを出した男の子より、設問を超えようとした女の子たちの方がある意味ではよほど倫理的で高度な考え方であると考えます。
Gilliganは純粋に心理学者としてKholbergの研究における女性の不当な扱いに抗議をしたに過ぎないのですが、これをきっかけに「女らしさ」、すなわち「女性的倫理」「女性的発想」「女性的知恵」による人間関係維持の能力を評価する研究が活発になります。
「女らしさ」を絶賛する事は、当然「男らしさ」の徹底的な批判にも繋がります。 例えば、心理学者のNancy Chodorowはフェミニズムと精神分析を組み合わせ、「男らしさ」は男の子が母親と自己の同一視をやめ、母親を否定する必要性から出る弊害だと考えました。 また、Evelyn Fox Kellyは男の子の幼児体験が「男らしさ」のイデオロギー、特に論理的思考への偏向の原因であると主張しました。 当然ながらここでいう論理的思考とは決してポジティブな物ではなく、人間的な感情を否定し、女性の抑圧を可能とする西洋文明の病原として批判する対象として挙げられました。
つまり、70年代後半のフェミニズム心理学の流れとしては、「女らしさ」の肯定に始まり、女性中心主義フェミニズムと同じく女性の感情や感性の肯定に繋がります。 これは、科学的手法をこそ唯一最高の知識の獲得手段と考える保守的な心理学者から見ると、学門としての心理学からの逸脱に他ならず、以後フェミニスト心理学に対する風当たりが強くなります。
90年代心理学とフェミニズムの乖離
こういう状況がしばらく続いたのですが、80年代に入ってから急速にアメリカ社会が保守化すると、心理学内部の状況も大きく変わりました。 特に90年代には生物学において遺伝子研究が進んだ事もあり、今やフェミニズム心理学が始まった頃から比べて心理学という学門のパラダイムが完全に変わってしまいました。 ここでは現在心理学の潮流と、フェミニスト心理学にとっての問題点を挙げてみましょう。
(1)科学主義
アメリカ心理学協会(American Psychological Association)では遥か以前から研究職の心理学者とカウンセラーら応用心理学の専門家が派閥争いを繰り広げていたのですが、昔は研究者が上級の会員としてそれなりの敬意が払われていました。 ところが70年代以降カウンセラーの数が急増し、ついに応用心理学者がAPAの主要な地位を乗っ取る事態になります。 それに怒った一部の学者がAPAを脱退して新たに「アメリカ心理科学協会」を作るなど、学界心理学者の反撃によって抗争が激化しています。
このため、学者でありながら社会的な問題に関心を抱くフェミニスト心理学者たちは抗争によって引き裂かれ、居場所を失っている例も少なくありません。 ジェンダー論の完成に大きな影響を与えたSandra Bemはフェミニスト心理学の中では最も一般に受け入れられた部類ですが、その彼女ですら「心理学か女性学かどちらか一方を選べという圧力を感じる」と語っています。
(2)医学主義
APAは診断のマニュアルとしてDSM(Diagnostic and Statistical Manual)を発行していますが、DSMに現われている考え方は、「精神的な疾患は肉体的な疾患と同質で、症状や原因を肉体的な疾患と同じ方法で記述・分類できる」というものです。 そうする事によって精神病を持った人が変な気がねなしに治療を受ける事ができるようになったという効果はあるのですが、精神的な苦痛の原因をあくまで個人の内面に求める形になりやすいという問題点がフェミニストセラピストによって指摘されています。 例えば、ある女性にとってうつの原因は夫から受ける暴力かも知れないのに、医学主義に陥った医者は原因は彼女の能内物質のバランスの欠如であるとして抗うつ薬を処方してしまうといった問題があります。
(3)遺伝子還元論
生物学での遺伝子研究は驚くほどのペースで進んでおり、近年になって人間の行動や思考を遺伝子に還元する考え方は心理学でも広まっています。 困った事に、それは男女の社会的性差をも遺伝子に還元する事に繋がり、70年代にジェンダー論が打ち破った「男性性」「女性性」を再び蘇らせてしまう事にもなってしまいます。 また、遺伝子による各人種の優劣や同性愛の遺伝子的原因といった考え方も以前より受け入れられるようになっていますが、これは多くの点でフェミニストたちが主張した社会的構築論・社会化の否定になります。
(4)進化心理学
遺伝子還元論をさらに極端にしたのがこの「進化心理学」という新しい分野ですが、最先端の研究者は進化心理学こそが精神分析の登場いらい長らくバラバラだった心理学を統一するパラダイムであると主張します。 ごく単純に説明すると進化心理学とはドーキンスの「利己的な遺伝子」論を心理学に応用したもので、すなわち人間の行動は遺伝子の自己保存に基づいているとする考え方です。
この考え方に従うと、男性が女性をレイプするのはそれが遺伝子に有利であるからだと説明されますし、決まったパートナーがいたとしても男性が多くの女性と関係を持ちたがるのも自然であるとされてしまいます。 進化心理学が問題なのは、「利己的な遺伝子」で説明する以上現状のほとんど全てが「自然である」として肯定されてしまい、変化を求めるフェミニズム心理学とはどうしても合わない点です。(注4)
以上のように現在の心理学とフェミニズムの潮流を見ると分かる通り、フェミニズム心理学の困難は現在の心理学とフェミニズムが全く逆の方向を向いているという事でしょう。 この乖離が続く以上、フェミニズム心理学は心理学の分野で認知されず、厳しい時代が続きそうです。
第2部 付記
注1:クライアントとの対等な関係
フェミニストセラピーが理論化される遥か前にMichel Foucaultはフェミニストによるカウンセリングを批判しています。 フェミニストは女性を解放すると言いながらカウンセラーとしてクライアントに接する事で医学的なディスクールを構築してしまい、いくらクライアントの身になって考えようとも権力構図から自由にはなれないと彼は主張しました。
ここで言われる「フェミニストによるカウンセリング」とは主に特殊な訓練を受けていない普通のカウンセラーによる物を指すと思われますが、ある人物がフェミニストであり同時にカウンセラーであったとしても、必ずしもフェミニストセラピーを実践している訳ではないという事は指摘しておきます。 厳密な意味でのフェミニストセラピーはフーコーの言うような問題を極力解決しようとした結果、既存のカウンセリングの枠組みをも超えようとしているのです。
ところで、Foucaultのこの主張はポストモダンフェミニズムの文献でちらっと読んだだけなのですが、原典を忘れてしまいました。 どなたかご存じの方がおられましたら、ご連絡くださるようお願いします。
注2:女性は不完全な男性?
現在の例では、アメリカ心理学会が定める診断マニュアル、DSM-IV (Diagnostic and Statiscal Manual, Revision Four)における人格障害の定義があります。 人格障害と診断されるのは、男性に多い「反社会性人格障害」(発生率は男性の6%、女性の1%と推定)を除いて圧倒的に女性が多いのですが、内容を見てみると受動的であること、消極的であること、ヒステリックであることなど、女性のステレオタイプを極端に拡大した物が人格障害とされているのに対し、男性のステレオタイプを拡大したものは上に挙げた反社会性人格障害しかありません。
女性に「女らしく」ない女性は異常であるとして「女らしさ」を強要しながら、本当に女性が「女らしく」振る舞うようになればまたそれを(男性を基準として)異常と呼ぶダブル・バインド的な社会の構図がある、というCheslerの鋭い指摘は今だに有効であると言えるでしょう。
注3:女性中心主義フェミニズム
女性中心主義を極限まで突き進めたのがMary Dalyの「Gyn/Ecology」(1978)ですが、より最近の例では女性解放と環境保護を一体としたエコフェミニズムがこの系譜に当たると思われます。 Dalyらの女性礼賛フェミニズムは、男性文明との関わりを一切拒否し、山の中で女神崇拝を基調とした小さなレズビアンコミュニティを作る所まで進みましたが、そのような事が可能なのは中流以上の家庭出身の白人女性がほとんどである一方、男性社会の中で抑圧と直面せざるを得ない貧しい女性を切り捨てる立場だと批判されました。 また、Dalyは女性の経験を強調するあまり全世界の女性の経験は同一である(よって彼女は全女性を代弁する事ができる)という過ちをおかし、黒人でレズビアンの詩人、Audre Lordeらに批判されました。 Lordeの批判は「Sister Outsider」(1984)に詳しいです。
注4:進化心理学
このページを公開してしばらくして、私が参加していた「人間の進化的理解研究会メーリングリスト」(現在は廃止)において「Macskaの進化心理学に関する著述は単純化し過ぎではないか」というご意見をいただきました。 それらを簡単にまとめると、(1)人間の様々な特性が遺伝にある程度還元されるとしても、それは環境や文化の影響を否定する訳ではない、(2)仮に性的差異が遺伝に還元されるとしても、それが性差別の擁護や固定化につながる訳ではない、(3)個々の行動が遺伝に有利である事は、その行動を正当化する事には繋がらない、という内容でした。
しかし、理論上はともかく現実問題として考えると、進化・遺伝の理論が伝統的に政治的な保守主義によって少数者を弾圧するために利用されてきた事は誰もが認める事実です。 結論として、進化心理学がそのように濫用されるのを防ぐためにも、心理学者や女性学者を含めた各方面の専門家が協力して対策を練るべきだという意見でまとまりました。
|
Copyright (c) 2000 Macska.org
E-mail: emerging@macska.org