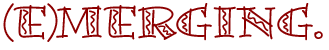
連載 『女性学』って何? 第1部
ペダゴジーとしての女性学
女性学って何?
女性学って何でしょう?
「女性についての学問」なんて答えがあるかも知れませんね。 確かに、歴史学が歴史についての学問で、心理学が人間の心理についての学問であるのなら女性学が女性についての学問でもおかしくないでしょう。 私は、女性学のこの側面を「科目としての女性学」と呼んでいますが、要するに伝統的なアカデミアで意識的・無意識的に正当な評価を受けていなかった女性及び女性による貢献にスポットライトをあてて再評価する、という事であって、アカデミックな女性学の重要な要素です。 これは、伝統的なアカデミアの欠落している部分を補完し、全体像を明らかにしようという形で、意外にも伝統的なアカデミアの側からの反発は少ない側面です。
「女性についての学問」としての女性学が生まれた背景には、1920年頃まで70年に渡って女性の参政権を求めて続いた第1次フェミニズム当時の記録が、男性中心の歴史学からきれいに忘れ去られていた事と無関係ではありません。 当時の女性が書いた本はすべて廃刊になっており、様々な集会や講演の記録も歴史家たちが一向に興味を示さなかったため、女性学がこれらを掘り起こす作業を始めるまでは第1次フェミニズムについてはほとんど知られていなかったのです。 女性についての過去の記録を発掘し、後世に残すためには女性による女性のための学問が必要だと考えたのも無理はないでしょう。
が、女性学には他の側面も存在します。 第2の側面が「方法論としてのジェンダー」と私が勝手に呼んでいるモノですが、既存の学問を「ジェンダー=社会的につくられる性」というベクトルで再分析するという側面です。 歴史学を例えにとると、今世紀初頭の頃の歴史学では、軍事・政治的なベクトルだけで歴史が語られていました。 後に経済的なベクトルや思想的なベクトルが加えられ、現在のような歴史学となったわけですが、女性学では同様にジェンダー及びジェンダー関係史を歴史学に取り込むよう要求します。 つまり、現在の歴史学ではある歴史的イベントに対して、その軍事的・政治的インパクトを分析するだけでなく経済的・思想的側面も叙述するようになりましたが、女性学的歴史学ではその歴史的イベントとジェンダーとの相互関係を研究します。
もう一つ例えを出しましょう。 国際政治学では通常、各国の軍事力・経済力が国家間のダイナミズムを作り出すという前提の下に様々な理論が立てられます。 そこでふと立ち止まって、「仮にジェンダーが今のような形でなかったら国際政治も変わるのではないだろうか」と考えるのが方法論としてのジェンダーです。 これは、単に「女性がリーダーだったら世界はもっと良くなっている」といった単純な物ではありません。 そうではなく、「資本主義が成り立っているのは、ほとんどの家事を女性が無償で行っているからではないか」「沖縄での米兵によるレイプ及び買春行為は日米安保の必然もしくは前提ではないか」「自由貿易が成り立っているは発展途上国の女性が奴隷のように酷使されているからではないか」というように、今まで個々の例とされてきたこれらの現象を一括して「世界を動かしているのは軍事力での政治力学でもなく、ジェンダーではないのか」という姿勢から考えるのが女性学的な国際政治学になります。
女性学のこの側面は、えてして伝統的なアカデミアから馬鹿にされてしまいます。 そりゃそうですね。 日米安保は軍事的な同盟(文化交流の側面もありますが)であって、沖縄の女性がレイプされる事は日米どちらの政府も望んでいません。 しかし、女性学は一部の米兵によるレイプや買春を個々の不幸な事件として放っておかず、一般性のある政治的事象として捕えます。 もし、レイプや買春が不可能だとしたら、米軍はそれでも沖縄に駐留するだろうか。 もし、男性米軍兵士の妻が米国でのキャリアを選択して沖縄に引っ越すことを拒否したら。 もし、アメリカ人の女性有権者がその政治的な力に目覚めたら。 これらの問いは一見飛躍した発想に見えますが、あらゆる事象を「ジェンダー」というベクトルで分析し、物事の今まで明らかでなかった側面を明らかにするのが「方法論としてのジェンダー」と呼ばれる女性学の側面です。
ペダゴジーとしての女性学
さらに、第3の側面として、ペダゴジー(教育技法)としての女性学があります。 これは多くの要素から成り立っていますが、大きな物としては生徒より教師が上に立つ「権威」の否定・平等主義、競争よりも協調の重視、そして経験に即した学習という要素があげられます。 それらについて説明する前に、伝統的なアカデミアにおける教育モデルについて復習してみましょう。
まず、一番古い型の教育モデルについて。 伝統的に欧米の教育制度では教師−生徒という上下関係を前提に、まるで港で船に荷物を積むように教師が生徒に一方的に知識を教えこむ、という積み荷型教育法がとられました。 これは生徒に対する教師の権威を絶対化する事で成り立つため、権威型とも呼ばれます。 前提として確かな「知」が教師の側にあるとされるため、生徒はこのモデルでは自主性を尊重されず、一方的に教師からの情報を受け取る船にさせられます。 権威は地位ではなくその知識と経験によってもたらされるとする考え方も出てきましたが、それも大きく分けると教師の絶対的権威を前提としているためこの型に分類されます。
次に現われた教育モデルが、現在アメリカの大学以降で一般的となっているリベラルアーツ教育、批判的思考と呼ばれます。 このモデルでは、生徒は自主性を尊重されるだけでなく、積極的に主張をするよう要求されます。 教師が一応の権威を持っていますが、生徒が論理でこの権威に挑戦する事が奨励されます。 教師に挑戦するだけでなく、生徒同士の間でも議論を闘わせる事が要求され、その独自性と積極性、そして論理の明快さを競争するわけです。 日本の評論家がアメリカの大学を褒める場合は大抵このモデルを指して褒めていると思われます。 「日本は『権威型』の教育を行っているため生徒の自主性が育たず、独創的なベンチャーが産まれない」なんて言う評論家、いますよね。
これらに対して、女性学はどのようなモデルを提示するのでしょうか。 まず、ペダゴジーとしての女性学は権威型モデルを正面から否定します。 女性学の背後にあるフェミニズムは平等主義を主張し、あらゆる絶対的権威に反対するからです。 第2部で詳しく述べますが、多くの女性学の学者は絶対的な真理や客観性、論理主義に基づいた「知」を否定するか、少なくとも懐疑的に見ており、教師の側に「知」があり、それを一方的に生徒に流し込めばよいとする権威型教育モデルとは前提を共有しません。
次に、第2のモデル、リベラルアーツ教育については、ペダゴジーとしての女性学はそれを部分的に取り入れつつも完全に受け入れません。 これはポストモダン主義の洗礼を受けてから特に頻著になった部分ですが、多くの女性学に関係する学者たちは、生徒及び教師が論理をもって議論という「競争」をするという行為自体を不毛と考え、より協調的な学習モデル(教師の権威を否定するため「教育」モデルとしては成り立たず、「学習」モデルと言い替えている)を提案します。 これも第2部で詳しく触れますが、批判的思考が相手の意見と自分の意見がどれだけ違うかを先鋭させ、主張を闘わせることに意義を見出すのに対し、女性学では相手の経験や社会的状況を思いやり、議論の善し悪しを別として、その人個人のコンテクストの元で理解し合う事を目的とします。
例えば、「男性なんてみんな自分勝手だ」という意見を持っている人がいるとします。 この意見に対し、批判的思考でアプローチするならば「一部の男性が自分勝手だからといって無制限に一般化するのは論理的に飛躍があり、間違っている」となるでしょう。 それに対し、女性学では「それは一般化しすぎじゃないかな」と指摘しながらも「間違っている」とは批判せず、逆に「でも、あなたがそう感じるほど自分勝手な男性と知り合っていたのならそれは理解する」と考えるわけです。 その上で、「一般化しすぎである」という事を気付かせるために「私は思いやりのある男性を知っているけどな」という感じに、「論理」ではなく「経験」を元に話します。 これを「肯定的思考」とでも呼びましょうか。 あ、これは原則としてあるだけで、女性学をやっている全員が守っているルールではないですから、女性学のグループで「フェミニストはみんな過激だ」と言ったら猛反発を受けるかも知れないのでご注意を(笑)
ペダゴジーとしての女性学は(女性学だけではないですが)、経験による学習を重視します。 教師や教科書に確かな「知」がある事を否定する以上、教科書を読んでいるだけでは勉強にならない、と考えるのです。 もちろん、教科書的な勉強を完全に否定するわけではないですが、女性学的アプローチを取る教師は社会科の見学や理科の実験、国語なら本を読むだけではなく実際に作家を講演に呼んだりするわけです。
これはある小学校の先生から直接聞いた話です。 そのクラスではある日算数の授業で直方体の「体積」を求める学習をやっていたのですが、先生は中が空洞になった紙の箱と、たくさんの1cm×1cm×1cm程度の小さなサイコロのような立方体を持ってきました。 先生はこの小さなサイコロ1つ1つが1立方センチメートルである事を説明します。 その上でグループに分けて、大きな箱の体積(正確には容積ですが、紙が薄かったため体積として扱っていたのでしょう)を求めましょう、という課題を出す訳です。
当然、児童たちは小さなサイコロがいくつ詰まるかで計算しようとする訳ですが、なかなか時間がかかります。 だんだん箱を大きくしながら何度も体積を求めていくうちに、児童たちは自然と「縦×横×高さ=体積」という方式を「発見」するわけです。 これが、経験に即した学習の例であり、ただ単に方式を教えられるよりずっと見に付くと思われます。
女性学ではこのように、理論だけを用いて経験と知識とが乖離する事を避け、経験と知識を融合しようとします。 それぞれが個人的な事として考えていた「経験」を分かち合う中で、個人的な経験と社会的なシステムの関係に気付き、自らの経験を元に「ジェンダー」の働きについて発見するのが女性学の目的です。
コンシャスネス・レイジングの功罪
なぜこのようなペダゴジーが発生したのでしょうか? なぜ女性学は「女性についての学問」「ジェンダーというフィルタを通した学問」にとどまらず、新たな教育モデルとペダゴジーを提案するまでに至ったのでしょうか? これは、女性学がどのようにして始まったのかにも大きな関係があります。
今でも「女性学」と「フェミニズム」を混同する人が多くいますが、それはそもそも女性学が第2次フェミニズムの波に乗って、その基本的な前提を受け継ぐ形で創始された事が原因と思われます。
70年代にアメリカで起こった第2次フェミニズムはマスメディアを舞台にした華やかな社会的革命であったとともに、地道な草の根活動を通した「静かな意識革命」でもありました。 全米女性機構が発足し、Gloria Steinem氏らが女性による女性のためのフェミニスト雑誌・Ms.誌を創刊したのもこの頃で、これらを通した全国的な連帯とは別にそれぞれの地域で小さなグループが次々と産まれました。
これらのグループは、コンシャスネス・レイジング(CR)グループと呼ばれます。 CRとは直訳すれば「意識を高揚させる」という意味ですが、何の意識かというと「ジェンダーによる抑圧」についての「意識」、あるいは「理解」です。 こうしたグループは参加者同士がお互いを尊重しながら自分の経験を語り、その中から共通項を探り出そうという性格の物で、根底には「すべての女性は等しくジェンダーによって抑圧されており、それを暴くことによってあらゆる女性は団結し、抑圧と闘う事ができる」という前提があったわけです。
女性が今の社会で女性として生きる上でふとその抑圧性に気付く経験、それを当時のフェミニズムでは「クリック」と呼んでいました。 これは、例えば暗い道を歩いていて絶えず周囲を警戒している自分に気付いた、という瞬間でもありますし、「どうやって育児と仕事を両立させようか」と悩んでいる時、ふと「何で私の夫は全然悩んでいないんだろう」と気付いた瞬間の事です。 第2次フェミニズムではこうした個人的な事が実はただ個人的なだけではなく、社会的・政治的に確立されたシステムであると主張し、「個人的な事は政治的だ」(Personal is Political)というスローガンを編み出しました。(注1)
大学のキャンパスで「女性学」という学問が登場したのもその頃で、それは当初CRのキャンパス版といった形態をしていました。 当時の女性学の行程を読むと、まず最初のページに「このクラスで聞いた他の人の経験をクラスの外の人に漏らしてはいけません」と、まるでグループ・カウンセリングかサポートグループさながらの事が書かれていて驚きます。 レイプや幼児期の虐待、配偶者による暴力などの経験について話す参加者もいたわけですからグループ・カウンセリングになっても仕方がないのでしょうが、あいにく女性学の教授にはカウンセラーの資格がありませんし、そもそもこれはクラスであってカウンセリングではありません。 そこで、行程には「このクラスはカウンセリングではありません」という注意書きもしてあります。
CRはサポートグループ的な面もあって疑似カウンセリングになっても構わないのですが、女性学は学問と名打っている以上そういう訳にもいきません。 第一、何か問題があれば資格もなしにカウンセリングもどきを行った大学側の責任問題になります。 そこで導入されたのが、「コ=カウンセリング」という概念です。 コ=カウンセリングとはヒューマニスティック心理学から借り受けた概念で、グループでお互いの経験を話すと同時に「無条件の肯定的な対応」(unconditional positive regard)を示し合う事がお互いの「癒し」に繋がるという考え方で、カウンセラー/クライアントという権力構造は必要なく、お互いが生身のある人間として参加すればよいという事になっています。 日本ではこの「コ=カウンセリング」と、それとは別の概念である「フェミニストセラピー」とが混同されている傾向がありますが、注意が必要でしょう。(注2)
とにもかくにも、「コ=カウンセリング」によってお互いの傷を癒し、団結して社会改革に向かうための「キャンパス版CR」「活動家養成講座」と位置付けられていた女性学ですが、意外な所からCRの活動自体が破綻します。 ほとんど白人・中流階級の女性だけが集まっていた最初の頃はうまく行ったのですが、貧困層出身の女性や少数民族の女性が参加するにしたがってCRの前提が崩れていったのです。
CRの前提とは、先に説明したように「すべての女性は等しくジェンダーによって抑圧されている」「ジェンダーの抑圧を暴く事で女性は団結する事ができる」という物でしたが、貧しい女性や少数民族の女性にとってはジェンダーの抑圧だけが問題ではありません。 言ってみれば当然ですが、彼女たちにとって本当に深刻なのは明日の食事であり、どこに行っても「自分を避けている」「肌の色が濃いから汚いと思われている」と感じる事だったのです。 中流階級の女性にとってポルノや売春は「女性の尊厳を汚す」と言っていればよいのですが、貧困層の女性にとってはそれは自分の姿であったり、自分の娘であったりするのです。
結果的に、CRによってすべての女性が「ジェンダーの抑圧」に対抗して団結するどころか、民族・階級的な「別の抑圧」が表面化し、白人・中流階級のフェミニストたちの無邪気なまでの欺慢が明らかになったのです。 もちろん彼女たちが差別主義だった訳ではないのですが、中流階級で白人の女性が貧困層の女性や少数民族の女性の経験を共有する事はついにできず、お互いが気まずい思いをしたままCRは空中分解して行きました(と言い切ると怒られると思うけど、私はそう思っているので書いてしまった)。
今となってみると、CRのおかげで貧困層出身の女性や少数民族の女性が白人・中流階級の女性によって独占されていたフェミニズムに参入し、「ジェンダーによる抑圧」から「すべての抑圧」へとフェミニズムの視野が広まったのは事実ですし、あの時代コ=カウンセリングのような女性同士の繋がりが必要だったのは確かでしょう。 現代アメリカ・フェミニズムは、「ジェンダーによる抑圧を強調するばかりに経済による抑圧や人種的抑圧を軽視してしまった」という事を原罪として背負いつつ、より広範で多様な運動へと脱皮したのです。 その意味で、大前提が崩れたとはいえCRにはそれなりの意義があったと言えると思います。(注3)
より広範で多様な女性学へ
アメリカにおけるフェミニズムがCRに見られる独善性に気付いた事で、当然の事ながらフェミニズム/CRを基本に置いていた女性学にも改革の嵐が吹き荒れます。 そして、その中でCRとは違った種類の女性学が生まれました。
1つはアカデミックの本流に戻り、伝統的な手法で「女性」にスポットライトを当てる「科目としての女性学」です。 これは、文学なら女性の作家や詩人に特に注目するクラスを作ったり、哲学で「フェミニズム思想」を研究する、という具合に、テーマを女性とする他は伝統的なアカデミアとほとんど同じ手法を取りました。 もちろん、学者が正教授に出世したり終身任官されるには伝統的な手法で研究し、伝統的な学術誌に論文を載せなければ駄目ですから、「真に画期的な事をするにはもっと安定した地位を築かなければいけない」と考えて一時的に理想をおあずけにした人もいたでしょう。
次に、それぞれの分野でジェンダー論を応用して分析に深みを持たせる「手法としてのジェンダー」があります。 この種の女性学は、考古学や文化人類学の資料を再検証して母系社会の構造を明らかにしたり、ヨーロッパにもあった地母神信仰を掘り起こしたり、過去に名作とされた文学作品に潜んだ男尊女卑的メッセージを指摘したりしました。
そして、教育学では女性学的ペダゴジーが「協調的学習」「経験的学習」という形で組み入れられており、特に小学校で様々な実験が行われています。 大学でもCRそのままの女性学授業はさすがにあまり残っていませんが、今では「話すこと」と同時に「聞くこと」を強調した形で一部の女性学のクラスが行われています。 「全員がジェンダーによる抑圧を共有している」というCRの前提があったうちは「話すこと」が何よりも重要だったのですが、その前提が不十分だったという反省から「他人の話を聞くこと」そして、「理解できない事を放っておかずに理解しようと努力すること」に焦点を合わせた新しい「ペダゴジーとしての女性学」が生まれたのです。
最後に、意図してなかった所でフェミニズムが白人・中流階級の偽善と化してしまった反省から、マルチカルチュラリズム(多文化主義)が女性学にも導入されました。 「ジェンダーによる抑圧」とのアナロジーから、人種的マイノリティや貧困層の人達が経験している「抑圧」も理解しよう、という試みで、多くの大学では「アフリカ系アメリカ人学」などの形となっていますが、これらは女性学から派生したと考えて構わないでしょう。 このようなアナロジーを使っての理解は、例えば「女性は『美しさ』という偽りの価値観によって社会的な成功を阻まれている」としたNaomi Wolf氏の「The Beauty Myth」の論理を流用し、アフリカ系アメリカ人の男性は「スポーツ」という価値観によって(プロスポーツで成功するごくわずかな例外を除いては)成功できないように仕組まれている、としたり、「女性の抑圧が『美の神話』なら、男性は『アメリカン・ドリーム』(=誰でもチャンスがあるのだから成功しないのは本人の努力が足りないのだとするイデオロギー)に呪われている」とする男性解放運動にのような形で実を結んでいます。(注4)
第1部 付記
注1:Personal is Political
このスローガンは左翼的な男性による社会運動から派生してきた唯物論的フェミニズムから提唱された物です。 当時の左翼運動に関わっていた男性たちは「資本主義が潰れれば自然と女性も解放される」としていたのですが、現に資本主義ではないはずのソ連や中国でちっとも女性が解放されていない事に気付いた人もいました。 その中から「女性は資本主義による家の外の抑圧と同時に、家の中でも不当な労働分担によって抑圧を受けている」と主張するFirestone、Milletのような唯物論的フェミニストが登場しました。 これをより一般化させると「個人的な関係(恋愛・家族)は政治的な関係でもある」となるわけです。
注2:CRからフェミニストセラピーへ
「全女性共通の経験」という大前提が崩れたCRはその後サポートグループに変貌していきました。 CRとサポートグループの大きな違いは、CRがお互いの共通項を探ることで社会の問題を暴きだし、社会的・政治的な変革を目指すのに対し、サポートグループは個々の内面を変革する事で社会に適応する事を目的としている事です。
ところで、過激な政治活動はしないもののCRの精神を受け継いで技術にまで高めたのがいわゆるフェミニストセラピーです。 フェミニストセラピーの主な特徴は、(1)文化的多様性に対する理解と配慮、(2)クライアントとの個人としての平等な関係、(3)セラピスト自身の責任ある自己管理、(4)社会的問題への関心、の4つが挙げられると思います。 フェミニストセラピーではクライアントとカウンセラーがお互いを個人として認め合う事を必要としていますが、ちょっと気を抜けば馴れ合いになったり、本来の目的を忘れてしまったりと問題が起きます。 フェミニストセラピーをするに当たってはそこまできちんと管理しなければならず、それなりの専門的な訓練が必要とされています。 そこがサポートグループであるコ=カウンセリングと本物のフェミニストセラピーの本質的な違いです。
注3:フェミニズムと人種差別
アメリカにおけるフェミニズムが白人中心主義と批判されたのはこれが最初ではありません。 第1次フェミニズムでも、フェミニストの多くは奴隷解放主義者ではありましたが、人種平等主義者ではありませんでした。 南北戦争後に黒人男性にも市民権が与えられるようになってからは「黒人の男性が白人の政治的支配を脅かす事を防ぐために白人女性にも参政権を与えろ」と、まるで黒人女性を完全に無視したかのような主張が堂々と行われたのです。 ギリシャなど貧しい南欧からの移民が増えた時も彼女たちは「アングロサクソンによる支配を維持するためにアングロサクソンの女性に参政権を与えろ」と主張しました。 南部では解放奴隷によるレイプの脅威を訴えKKKによる黒人リンチ殺人に同調したフェミニストたちもいたくらいです。 第1次フェミニズムにもSoujourner Truthのような素晴しい黒人女性活動家がいたのですが、白人のフェミニストから疎まれ、結局人種的和解はなりませんでした。
第2次フェミニズムでは作家のAlice Walker氏や詩人のAudre Lorde氏らが「アフリカ系アメリカ人女性の経験」を元としたアフリカ系アメリカ人フェミニズムの体系を築くことに成功しましたが、それでも白人中心主義的な思考は根強く残っています。 まぁ、一般社会にくらべてフェミニズムの方が平等主義的である事は間違いないのですが。
さて、アメリカの人種的マイノリティで独自のフェミニズム理論を確立したのは今の所アフリカ系アメリカ人だけですが、「大家族制とカトリック信仰」「言語的違和感」を中心テーマとしたラティーノ・フェミニズムや気の遠くなるような多様性を内包したアジア系アメリカ人フェミニズムも90年代に入ってから生成に向かっています。 アジア系アメリカ人フェミニズムについては私も勉強を始めている所ですが、多種多様な文化・言語・慣習・人種・宗教が混在するアジアの伝統をアジア系アメリカ人の目で見る事により、これまでの西洋の補完物としてのステレオタイプ的な東洋のイメージを乗り越えた新しいアジア観が生まれてきそうで楽しみです。
注4:Naomi Wolfと「The Beauty Myth」
「The Beauty Myth」(1992)では、女性の成功を妨げる「美の神話」として、「普遍的な『美』という価値観が存在する」「女性が成功するには『美』が必要だ/女性は『美』を手にする事で成功できる」「『美』は、努力すれば誰でも手にする事ができる/美しくないのは本人の努力が足りないからだ」というような隠されたメッセージを送るメディアによる暗示を指摘しています。 Wolf氏は、女性は自らの意思でダイエットしたり化粧をしたりしたつもりでいるが、実はメディアや企業によって送られるこうしたイデオロギーを内部化しているのだと主張するのです。
「女性によって内部化された抑圧」は、ほぼ同時期にベストセラーとなったSusan Faludi氏の「Backlash」(1992)にも共通したテーマなのですが、これらの本が出版された歴史的背景として、性差別を禁止する新しい憲法修正条項(ERA)が80年代当初に挫折し、フェミニストたちがその失敗の原因を突き止めようとしていた事を指摘しておきます。
さて、「The Beauty Myth」ではダイエットをする女性をカルト宗教の信者に例えたり、摂食障害の被害者をホロコーストの犠牲者と較べるなど過激なアナロジーで批判を浴びたWolf氏ですが、数年後に出版された「Fire With Fire」(1994)では鮮やかな転向を見せます。 例えば、「Fire With Fire」でのWolf氏は「今やっと女性に成功のチャンスが与えられているのに、フェミニズムが女性の被害ばかりを強調しているとせっかくのチャンスを見逃す事になる」としてCatharine MacKinnon氏ら「被害者フェミニズム」を批判しました。 さらに、彼女は「美」の問題でも「女性一人一人の決断を男権主義の産物としてではなく、彼女自身の決断として認める新しいフェミニズムが必要だ」と、「The Beauty Myth」とは正反対の事を主張しました。
「Fire With Fire」の特徴は、女性がビジネスの世界で成功するためには、学閥で繋がった男たちのエリート社会(これが、Faludi氏の言う「ガラスの天井=女性がいくら頑張っても踏み込めない男性エリート社会の壁」の一部でもあります)に対抗して、女性同士のグループで情報を共有し、便宜を図り合うべきだとする現実的な提案でしたが、これは、実際に活躍しているビジネスウーマンに支持されましる一方、従来の彼女のファンからは「エリート主義的だ」と批判されました。
|
Copyright (c) 2000 Macska.org
E-mail: emerging@macska.org